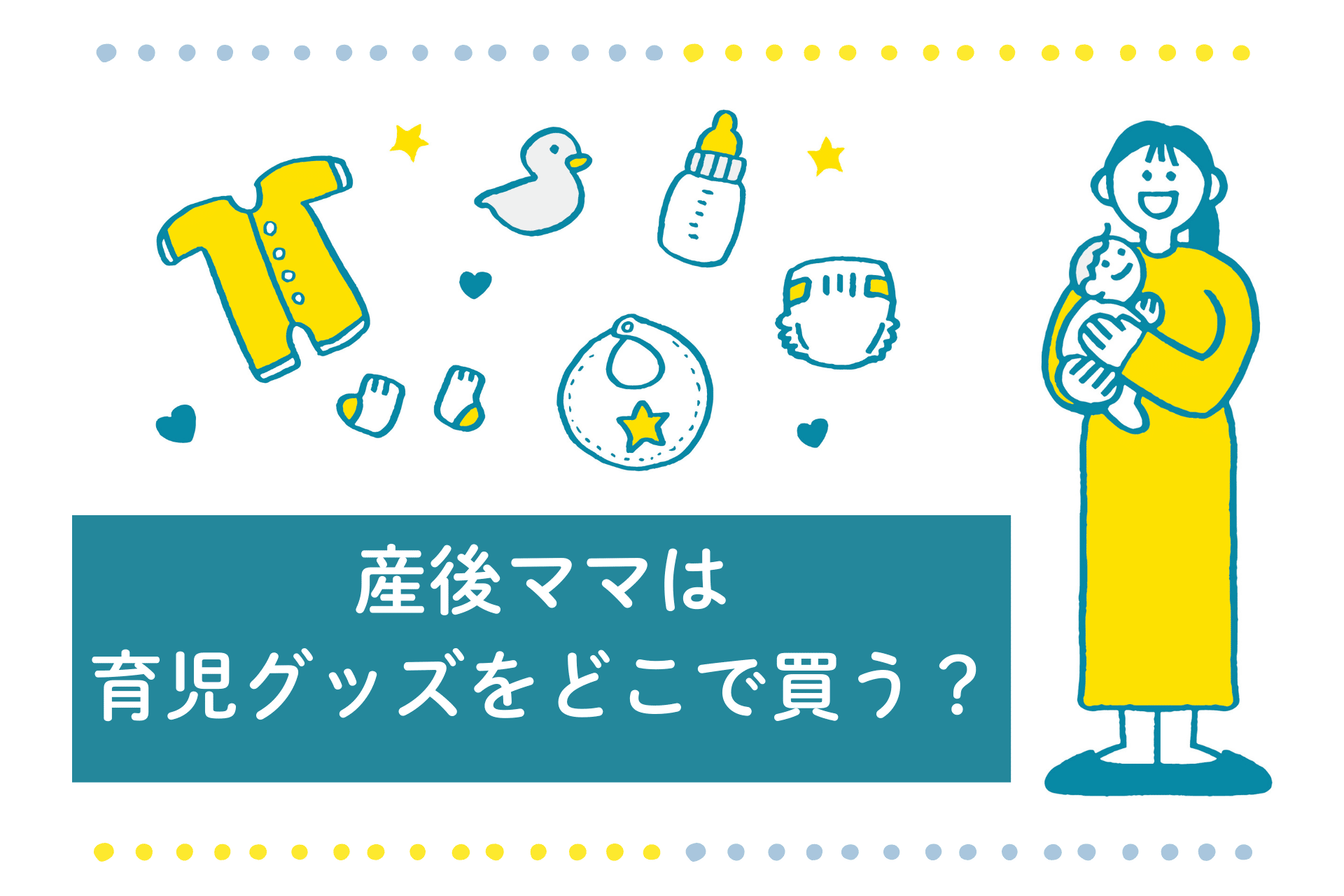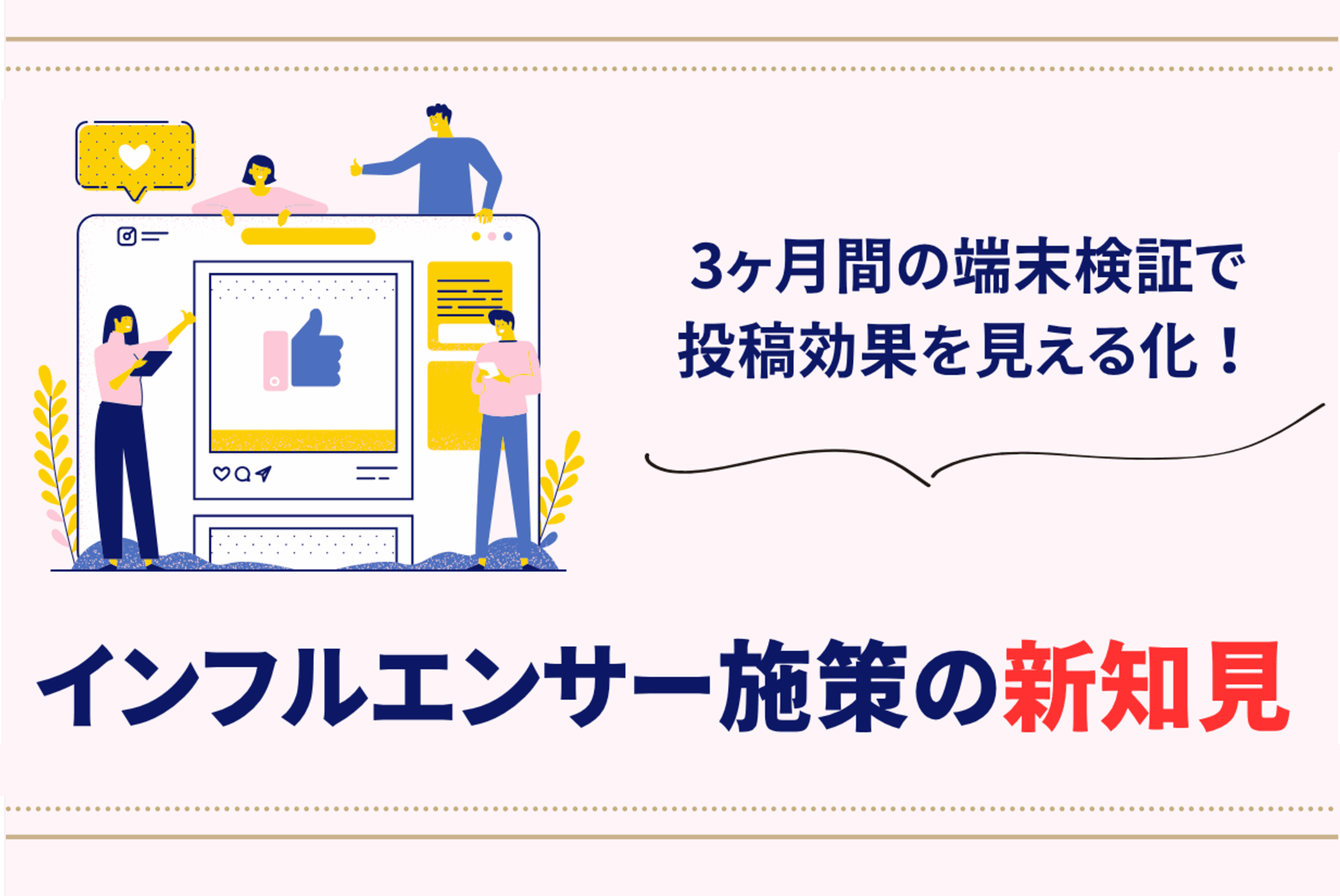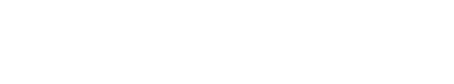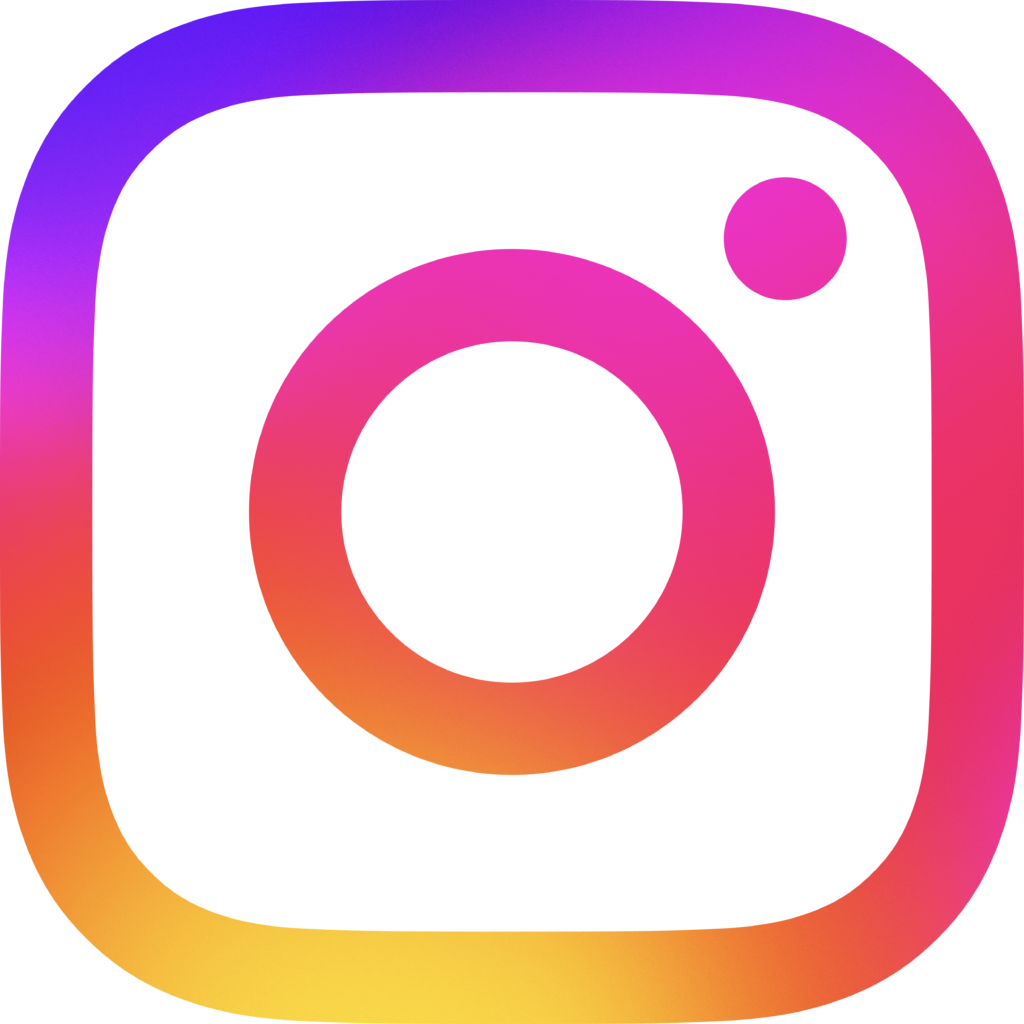赤ちゃんの鼻水や鼻づまりは、成長の中でよくあるお悩みのひとつです。
まだ上手に鼻をかめない赤ちゃんにとって、鼻が詰まるだけでもミルクが飲みにくくなったり、夜ぐっすり眠れなくなったりと、さまざまな影響が出てしまいます。
本記事では、赤ちゃんの鼻水・鼻づまりについて、原因や症状の見分け方、自宅でできるケア方法まで、看護師の視点を交えてわかりやすく解説します。
本記事でわかること
・赤ちゃんの鼻水・鼻づまりの主な原因
・症状からわかる見分け方のヒント
・自宅でできるケアや鼻水吸引のコツ
大切な赤ちゃんが少しでも快適に過ごせるよう、ぜひ日常のケアに役立ててくださいね♪

記事の監修者:小栗 望
【実績】
2019年に看護師免許を取得。
これまで、総合病院で外科を中心に勤務し、その後小児のワクチン接種や保育園での業務経験があります。
趣味は読書や料理、ワインです。海を渡ってワイナリーを訪問することもあります。
赤ちゃんの鼻水・鼻づまりの原因とは?
赤ちゃんはまだ身体の機能が未熟なため、ちょっとした刺激でも鼻水が出たり、鼻が詰まりやすくなったりします。
赤ちゃんの鼻水・鼻づまりの主な原因について詳しく紹介しますので、確認しましょう。
風邪による鼻水・鼻づまりの特徴
赤ちゃんの鼻水の原因は、風邪によるウイルス感染が関係しているケースが多いとされています。
特に生後6か月〜1歳未満の赤ちゃんは免疫力が十分に備わっていないため、風邪をひきやすく、鼻水や鼻づまりが起きやすい傾向があります。風邪の初期段階では、透明でサラサラとした水のような鼻水が出ることが多いです。
また赤ちゃんは口呼吸がまだ上手にできないため、鼻が詰まるとミルクが飲みにくくなったり、睡眠が浅くなったりすることも。日々の様子を丁寧に観察しながら、必要に応じて小児科などの医療機関に相談しましょう。
アレルギーが原因のケースも
赤ちゃんの鼻水は、風邪以外にもアレルギー反応によって生じることがあります。
特にハウスダストや花粉、動物の毛などに反応して、透明で水のような鼻水が長引くことも。家庭内でペットを飼っている場合や季節の変わり目に症状が強まる場合は、環境による影響を受けやすい状態かもしれません。
また家族にアレルギー体質の方がいる場合、赤ちゃんもその傾向を受け継いでいる可能性があるため、症状が繰り返される場合は一度医療機関に相談してみると安心です。
乳幼児のアレルギー性鼻炎については、成長に伴って軽快するケースもありますが、早めに対策をとることで赤ちゃんの生活がより快適になるでしょう。
その他(月齢・環境・発達)による影響
赤ちゃんの鼻水や鼻づまりは、風邪やアレルギー以外にも、成長段階や周囲の環境に影響されて起こることがあります。
鼻の構造がまだ小さく未発達なため、わずかな刺激でも鼻が詰まりやすいのが特徴。生活環境の温度差や乾燥、発達に伴う変化(よだれの増加やうつ伏せの姿勢など)も鼻の状態に影響を与える要因となります。
以下の表に、月齢や環境、発達に関連して見られる鼻水・鼻づまりの原因をまとめました。
| 要因の種類 | 主な内容 | 鼻水・鼻づまりとの関係 |
| 月齢の低さ | 鼻腔が狭く粘膜が敏感 | 鼻が詰まりやすく、少量の鼻水で苦しそうに見えることがある |
| 室内の乾燥 | 冬場や冷暖房による湿度低下 | 鼻の粘膜が乾燥し、粘り気のある鼻水が出ることがある |
| 気温の変化 | 外気との寒暖差 | 刺激で一時的に透明な鼻水が出ることがある |
| 発達の影響 | よだれの増加、ミルクの逆流、うつ伏せ寝 | 鼻や喉に刺激が加わり、鼻水が出ることがある |
赤ちゃんの鼻の状態は非常にデリケートで、外部からの刺激や日々の成長の中でも変化しやすいです。日々の観察を大切にしながら、快適な環境づくりを意識していくことが、赤ちゃんの呼吸をサポートするポイントになります。
鼻水の種類でわかる!症状の見分け方
赤ちゃんの鼻水には、色や粘度、量などにさまざまな違いがあります。
看護師の視点も交えながら、鼻水の種類からどのような症状が考えられるのか、判断のヒントをご紹介します。
看護師が解説|鼻水の色・粘度からわかる健康サイン
鼻水の色や粘度は体調のバロメーターです。
鼻水の性質や食欲、機嫌などに変化があれば早めの受診をおすすめします。
| 鼻水の特徴 | 考えられる原因 | 対応・注意点 |
| 透明でさらさら | アレルギー性鼻炎、風邪の初期 | 刺激物を避け、悪化しなければ様子を見る |
| 白く濁っている | 風邪の進行、軽い炎症 | 色や粘度が変化しないか、食欲、機嫌など症状の経過に注意 |
| 黄色〜緑で粘り気がある | 風邪、細菌感染、副鼻腔炎など | 数日続く場合は耳鼻科受診を検討 |
| 血が混じる | 鼻粘膜の乾燥や傷、鼻を強くかみすぎている | 加湿・保湿、鼻を強くかまない、出血が続く場合は医療機関へ |
くしゃみや咳を伴う場合の注意点
赤ちゃんの鼻水に加えてくしゃみや咳が見られる場合は、体が何らかの異物やウイルスに反応している可能性があります。
特に以下のような症状が見られる場合は、慎重な観察が求められます。
| 観察される症状 | 考えられる状況 | 注意点 |
| 頻繁なくしゃみ | 鼻の刺激やアレルギー反応など | 他に症状がなければ様子を見てもよいが、長期化する場合は専門家に相談しましょう。 |
| コンコンという軽い咳 | 鼻水が喉に落ちることで反射的に咳が出ていることも | 機嫌や食欲に問題がなければ経過観察しましょう。 |
| ゼーゼー、ヒューヒューといった音を伴う咳 | 気道が狭くなっている可能性(喘鳴) | 呼吸が苦しそうな場合は早めの受診を検討してください。 |
赤ちゃんの咳やくしゃみは、軽い症状であることも多い一方で、呼吸器に関わる重い症状の前触れになることもあるため、見過ごさないことが大切です。
特に呼吸が浅く早くなっていたりミルクの飲みが悪くなるなど、普段と違う様子がある場合は、速やかに医療機関に相談するようにしましょう。
熱がない場合の判断ポイント
赤ちゃんに鼻水や鼻づまりの症状が見られても、発熱がない場合は対応に迷うことがあるかもしれません。熱がないからといって完全に安心とは言い切れませんが、以下のポイントを参考にして注目してみましょう。
| 判断ポイント | 注目ポイント | 判断のヒント |
| 機嫌 | 普段通り笑ったり反応が良いか | 機嫌が良ければ大きな問題でないことが多い |
| ミルク・母乳の飲み方 | しっかり飲めているか | 飲みが悪い場合は注意が必要 |
| 睡眠の様子 | よく眠れているか、途中で何度も起きないか | 鼻づまりで眠りが浅い場合は対処を検討 |
| 鼻水の性状 | 透明で量が多すぎないか | 色や粘度に変化があれば経過を注視 |
発熱がなくても、赤ちゃんの様子に「いつもと違う」と感じる変化がある場合は、無理せず小児科などの医療機関に相談することが重要です。
自宅でできる鼻水・鼻づまりのケアと対処法
赤ちゃんの鼻水や鼻づまりは、必ずしもすぐに病院を受診する必要があるわけではありません。軽い症状であれば、家庭でできるケアによって赤ちゃんの呼吸を楽にしてあげることができます。
加湿や鼻水の吸引など、自宅でできるシンプルかつ効果的なケア方法をご紹介しますので、赤ちゃんの状態に合わせて、無理なく取り入れてみてください。
濡れタオルや加湿器を使ったケア方法
乾燥した空気は、赤ちゃんの鼻粘膜を刺激し、鼻水や鼻づまりを悪化させる一因になることがあります。そのため室内の湿度を適切に保つことは、鼻づまりを和らげる基本的な対策のひとつです。
また加湿だけでなく、部屋の温度管理や空気の清浄にも気を付けることで、赤ちゃんの呼吸がより快適になる環境づくりが可能。湿度を意識したケアは、赤ちゃんの体調管理だけでなく家族全体の健康にも役立ちますよ。
鼻水を吸引する
赤ちゃんの鼻づまりが強いと、ミルクが飲みにくくなったり、眠れなかったりと日常生活に支障をきたすことがあります。
自宅でも手軽にできる対処法の一つが、鼻水を吸引するケアです。市販されている鼻水吸引器を使えば、家庭でも無理なく吸引を行うことができます。使用する際は、赤ちゃんの負担をできるだけ少なくすることを心がけましょう。
| 項目 | 内容 |
| タイミング | ミルク前やお風呂上がりなど、鼻水が柔らかくなっている時が理想的 |
| 回数 | 1日2〜4回程度が目安。吸いすぎには注意 |
| 吸引器の種類 | 口で吸うタイプ、手動ポンプ式、電動タイプなどがある |
| 吸引時の姿勢 | 赤ちゃんを仰向けに寝かせ、軽く頭を支えながら行う |
| 注意点 | 強く吸いすぎないこと。嫌がる時は無理せず中断を |
吸引器を使う際には、必ず清潔な状態を保ち、使用後は部品をしっかり洗浄・乾燥させることも忘れずに。
夜中に寝れないときの対処法
夜間は気温や湿度が下がりやすく、鼻づまりが悪化しやすいことも。夜中に寝れないときの対処法として、加湿を保つことなどがあります。
◆夜間ケアの工夫とポイント
| 方法 | 内容 | 注意点 |
| 頭を少し高くする | タオルなどで枕元を少し傾けることで、鼻水が喉へ流れやすくなる | 首が過度に曲がらないよう高さは控えめに |
| 加湿を保つ | 加湿器や濡れタオルで部屋の湿度を50〜60%程度に保つ | 湿度が高すぎるとカビの原因になるため注意 |
| 寝る前の吸引 | 寝る直前に軽く鼻水を吸っておくと呼吸がしやすくなる | 吸引しすぎないこと、赤ちゃんの機嫌を見ながら実施 |
夜間のケアは、赤ちゃんの安眠を守るだけでなく、保護者の負担を軽減する意味でも重要です。落ち着いた環境で、赤ちゃんが安心して眠れるようサポートしていきましょう。
【看護師さん助言】医療機関を受診すべきサインとは
医療機関を受診すべきサインを知っておくことで、いざという時に対応ができ、赤ちゃんの健康を守れるでしょう。
現役の看護師さんの助言もありますので、ぜひチェックしてくださいね!
症状が何日続いたら病院へ行った方がいい?
赤ちゃんの鼻水が数日続いても、機嫌が良く、食欲や睡眠に問題がなければ、家庭でのケアを続けながら様子を見ても大丈夫です。しかし、以下のような場合は医療機関を受診しましょう。
- 黄色や緑色の鼻水が出る
- 鼻水がドロドロしている
- 母乳やミルクが飲めない、食欲がない
- 眠れない
これらの症状がなく緊急性がない場合でも、医療機関で適切な治療を受けると鼻水が改善する場合もあります。
緊急性の高い症状の見極め方
以下の症状が見られる場合は、すぐに医療機関を受診するか救急対応を検討してください。
- 呼吸が苦しそうで肩で息をしている、呼吸が速い
- ぐったりしている、反応が鈍い
- 唇や顔色が青白い、紫色になっている
- 高熱が続いている
- けいれんを起こしている
赤ちゃんの様子を注意深く観察し、これらのサインが見られた場合は速やかに医療機関を受診しましょう。
赤ちゃんの鼻水に関するよくある質問
赤ちゃんの鼻水や鼻づまりについては、ママやパパの多くが同じような疑問や不安を抱えています。鼻水吸引の頻度やケアの方法、市販グッズの活用まで、育児中に直面するリアルな悩みは尽きません。
家庭で役立つヒントや注意点を、現役の看護師さんがQ&A形式でわかりやすく回答していますので、ぜひチェックしてみましょう!
鼻水吸引は1日何回くらいがベスト?
吸引する頻度は、1日2〜4回程度が目安ですが、鼻水の量や赤ちゃんの様子によって調整するのが大切です。
特に以下のようなタイミングで行うのが効果的です。
・起床時(睡眠中は鼻水が溜まりやすい)
・授乳や離乳食の前(むせにくくなる)
・入浴後(分泌物が柔らかくなって吸引しやすい)
・寝る前(呼吸が楽になり寝付きが良くなる)
ただし、鼻水がどんどん出てくる場合は、回数にこだわらず適宜吸ってあげましょう。
赤ちゃんは自分で鼻をかむことができないため、吸引することで呼吸を楽にしてあげたり、ミルクや母乳を飲みやすくしてあげることが大切です。
吸引しすぎはNG?
吸引のしすぎは、NGです。
1回の吸引時間が長すぎたり、回数が多すぎたりすると鼻の粘膜を傷つけてしまう可能性があります。その結果、以下の症状が発生するリスクがあります。
・粘膜を傷つけて出血する
・炎症を起こす
・赤ちゃんが嫌がってストレスになる
手動でも電動でも、「無理なく、優しく」が基本です。
市販の鼻水吸引器って実際どうなの?
市販の吸引器でも十分に効果があります。主に以下のタイプがあります。
⚫︎口で吸うタイプ、手動タイプ
メリット:コスパが良く、吸引力を調整しやすい。初期段階におすすめ。
デメリット:保護者が風邪をもらう可能性がある。奥にある鼻水までは取りきれない。
⚫︎電動タイプ
メリット:吸引力が強く、連続的に使える。鼻水が多いときや、何度も使う家庭に便利。
デメリット:吸引力が強く、慣れていないと鼻粘膜を傷つける可能性がある。高価なものが多い。
吸引器によって吸引の強さなどが異なるので、赤ちゃんに合った吸引器を選びましょう。
透明な鼻水でも注意が必要な場合はある?
透明な鼻水の場合、少し様子を見た方がいいのではと思うこともありますよね。
しかし、以下のような場合は注意が必要です。
- 1週間以上続く
- 呼吸が苦しそう・咳や熱を伴う
- 授乳や睡眠に支障が出ている
これらの症状が出ていなくても、放っておくと中耳炎や慢性的な副鼻腔炎に繋がる恐れがあります。心配な場合は、必要に応じて受診しましょう。
鼻水・鼻づまりと上手に付き合って赤ちゃんを楽にしてあげましょう!
赤ちゃんの鼻水や鼻づまりは、成長の過程で誰もが経験する自然な現象のひとつです。家庭でも取り入れやすい加湿や吸引ケアを活用することで、赤ちゃんの呼吸が楽になり、睡眠や授乳の質も改善されることがあります。ただし、症状が長引いたり、他の体調変化を伴う場合には、無理せず医療機関に相談しましょう。
赤ちゃんはまだ自分で不快を伝えることができません。だからこそ、保護者の気づきや対応が何よりも大きな支えになります。少しでも楽になるように、できる範囲で優しく寄り添いながら、鼻水・鼻づまりと上手に付き合っていきましょう。